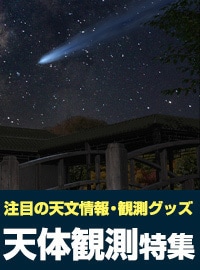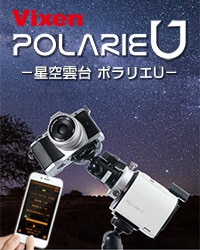彗星特集2025 注目のレモン彗星を見よう
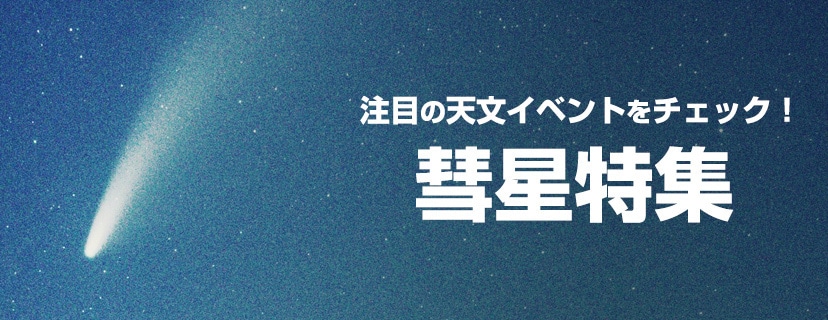
【目次】
・今年見られる彗星
・彗星とは
・双眼鏡で観察する
・天体望遠鏡で観察する
・カメラで撮影する
2025年10月 レモン彗星
レモン彗星(C/2025 A6)は2025年1月に米・レモン山天文台での観測によって発見された非周期彗星です。8月中旬に急増光し、双眼鏡で見えるクラスの彗星になりました。そのレモン彗星が10月中は観測チャンスとなります。
上旬から中旬はおおぐま座からりょうけん座へ移動し、未明から明け方の北東の空で見られます。明るさは月初めに約7等、ピークの20日ごろには4等まで明るくなると予測されています。
また、15日ごろからは、夕方から宵の北西から西の空でも4等前後の明るさで見えるようになるでしょう。りょうけん座からうしかい座、へび座へと移動し、21日の地球最接近の前後は日々の見かけの運動量が大きくなります。
彗星は太陽系外縁からやってくるとされる小さな天体です
彗星とは、夜空に長い尾を引いている天体のことです。日本ではその姿がほうきに似ていることから「ほうき星」とも言われています。彗星は、本体の大きさが数キロメートルから数十キロメートルのとても小さな天体です。成分はおよそ8割が水(氷の状態)で、二酸化炭素、一酸化炭素、その他のガス、そして微量のチリから成ります。地球をはじめとした惑星と同じく太陽系を構成する天体の一種ですが、他の天体と異なる大きな特徴として、公転軌道が細長い楕円や放物線・双曲線を描くことが挙げられます。
放物線や双曲線の軌道を描く彗星は、太陽に近づくのは一度きりで二度と戻ってこない(回帰しない)彗星です。また、楕円軌道をもつ彗星は公転周期が200年以内の「短周期彗星」、それよりも長い「長周期彗星」に分けられます。

彗星の姿と輝く仕組み
彗星の主成分は氷で、表面に砂がついた「汚れた雪だるま」にたとえられます。太陽に近づくと、その熱で彗星の核の表面が少しずつ溶けて崩壊します。蒸発した核の氷と、内部のガスや塵が一緒に表面から放出され、大気を作って覆い始めます。その結果、彗星の本体が「コマ」と呼ばれる淡い光に包まれて輝いて見えます。
さらに、本体から放出されたガスと塵がほうきのように見える「尾」を作ります。彗星の尾は、その成分と見え方から大きく2種類に分けられます。一つは、ガスがプラズマ化した「イオンの尾」です。放出された電気を帯びたイオンは、太陽風に流されて太陽とは反対の方向に細長く伸びます。もう一つは、塵が作る「ダストの尾」です。放出された塵は、太陽の光の圧力を受けて太陽とは反対の方向に伸びますが、塵のサイズによって圧力の受け方が異なるために、彗星の軌道面に広がった幅のある尾になり、イオンの尾とは異なる様子になります。
彗星は、太陽に近づくにしたがって核の表面温度が上がるため、明るく、尾も長くなっていきます。地球と太陽との距離と同じくらいまで接近すると、いよいよコマや尾が目立って観測され始めます。しかし、太陽に近づいた際に、どの程度明るくなるか、地球からどのように見えるかは、彗星本体のサイズや表面の状態、成分、さらに地球との位置関係によっても異なるため、正確な予測は難しくなっています。

彗星の名前について
20世紀初頭から、彗星の名前には「発見者の名前」を付けるということが一般的になりました。現在は報告の早い順に最大3名の名前や天文台・プロジェクト名を付けることができます。一方で同じ人やグループが複数の彗星を発見する場合もあり、これまでに発見されていた彗星の名前と混同する可能性があるため、正式名称として符号も付けられています。

例えば2013年に接近したパンスターズ彗星は「C/2011 L4 (PANSTARRS)」という表記になります。
最初の「C/」は発見後すべての彗星に付けられます。「C」は、Comet(彗星)を表します。その後、公転周期が200年以下の周期彗星と認められた場合は「P/」に変更されます。その後に、発見された年号と、発見時期を表すアルファベット(月の前半・後半で分けられています)、その時期何番目に発見されたかを表す数字が付けられ、符号の後には括弧書きで発見者名前が表記されます。
また、ポン-ブルックス彗星のように、2回目の回帰が観測された彗星には「P/」の前に通し番号が付けられます。
彗星を観察するときは、その日におおよそどの方角のどのくらいの高さに見えるかを調べておくことが大切です。彗星は淡い天体であるため、街明かりや街灯があると見えなくなってしまうことがあります。また、20~30分強い光を見ないなど暗闇に目を慣らしておく必要があります。特に低空に見える彗星は肉眼で探すのが難しいこともあるため、チャンスを逃さないためにも双眼鏡などを持って出かけましょう。
双眼鏡があれば肉眼では見えにくい明るさの時期でも、彗星の核やコマ、尾の状態まで見やすくなります。明け方に見るのであれば東側の空が開けた場所、夕方に見るのであれば西側の空が開けた場所が最適です。双眼鏡を選ぶときは、暗いシーンでもブレにくく、小さな星の光を捉える集光力の高いモデルがおすすめです。倍率8倍以下、対物レンズ口径32mm以上を目安に選ぶと良いでしょう。三脚に取り付けられる双眼鏡であれば、より長時間安定した視界で観察を楽しめます。
大口径の双眼鏡なら肉眼では見えない小さな星、淡い彗星の光も見えてきます。星空を広く見渡せるように設計された超低倍率の双眼鏡もラインアップされています。また、マルチコートが施されている双眼鏡なら色のにじみも最小限に抑えてくっきり見ることができます。

大口径の双眼鏡はやはり長時間空に向けていると腕が疲れてしまいます。そのため、ビノホルダーやアダプターを使用して三脚にセットして覗くのがおすすめです。特に家族や友達と観察に出かけた際は、彗星の見える位置から双眼鏡を動かさずに交代できるため、同じ視点を共有でき、より観察を楽しめます。

圧倒的な明るさとコストパフォーマンスの大口径モデル
手持ちでも安定した視界が得られる手ブレ補正つき双眼鏡
大口径でも持ち運びやすい低倍率単眼鏡
天体望遠鏡で観察する場合は、なるべく口径の大きなもので倍率を低くしてみることをおすすめします。双眼鏡と違い天体望遠鏡は倍率が高くなるので、視野が狭くなってしまうためです。彗星は淡い天体のため視野が狭くなると見つけるのが難しくなります。そのため低倍率にして、なるべく広い視野で見たほうが確認しやすくなります。まず双眼鏡で彗星を見つけておくと位置を決めやすくなるため、天体望遠鏡で観察する際は双眼鏡もセットで持って行くと良いでしょう。
天体望遠鏡の倍率は本体(鏡筒)の焦点距離とアイピース(接眼レンズ)の組み合わせによって決まり、通常天体望遠鏡には2本以上のアイピースが付属しています。アイピースは使用中にも簡単に着脱できるため、しっかり位置決めをすれば倍率を変えて観察することも可能です。天体望遠鏡を選ぶ際は、どんなアイピースが付属するかも確認しましょう。

天体望遠鏡の鏡筒を固定する架台には、カメラの三脚と同様に操作するものや、自由に動かせて手を離すとその場で止まるフリーストップ式、それに加えてダイヤルを回すように位置を微調整できる微動ハンドル付きのものなどがあります。星空は時間経過とともに動いていきますが、微動ハンドルなら追いかけ続けるのも快適です。





























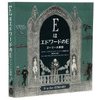
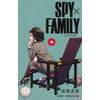
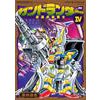
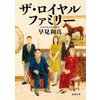




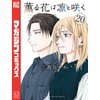

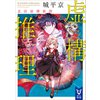































































![MAK70C FAST [天体望遠鏡 VOYAGER MAK70FAST]](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/008/487/399/100000001008487399_10205_001.jpg)